「株式投資で大きな成功を収めたいけど、どの銘柄を選べばいいか分からない…」
そんな悩みを抱える投資家は多いのではないでしょうか。
伝説的な投資家ウィリアム・J・オニールが開発したCAN-SLIM(キャンスリム)は、歴史的に大きな株価上昇を見せた「スーパーパフォーマンス銘柄」に共通する7つの特徴を体系化した、強力な成長株投資法です。
この記事では、CAN-SLIMの7つの基準を一つずつ、初心者にも分かりやすく解説します。この法則を理解すれば、あなたの銘柄選定の精度はきっと大きく向上するはずです。
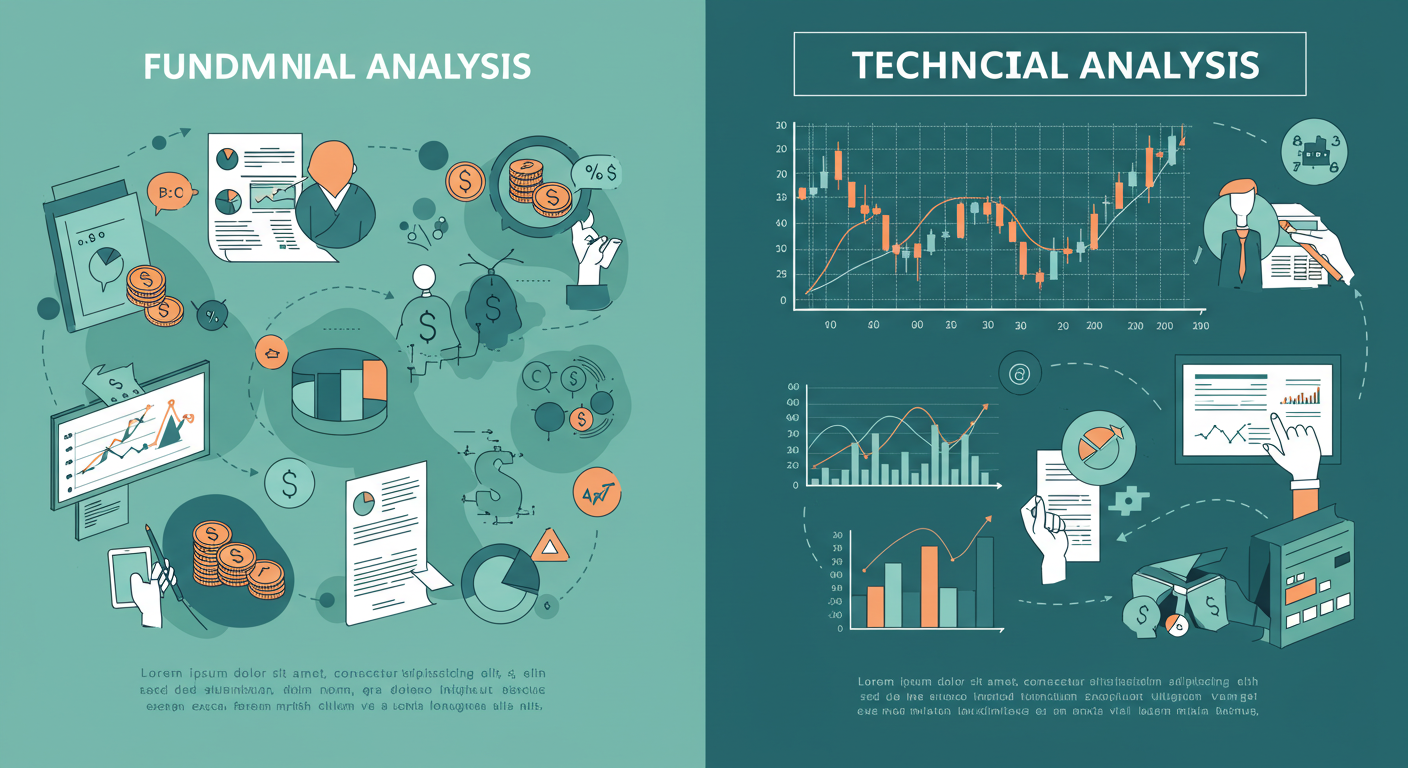
CAN-SLIM投資法とは?
CAN-SLIMは、米国の著名な投資家ウィリアム・J・オニールが、100年以上にわたる米国株式市場のデータを分析し、大化けした銘柄に共通する特徴をまとめた投資手法です。
彼の著書『オニールの成長株発掘法』で詳しく解説されており、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせた、非常に実践的なアプローチとして世界中の投資家に支持されています。
CAN-SLIMは、以下の7つの基準の頭文字をとったものです。
- C - Current Quarterly Earnings(当期四半期利益)
- A - Annual Earnings Growth(年間利益成長)
- N - New Products, New Management, New Highs(新製品、新経営陣、新高値)
- S - Supply and Demand(株式の需要と供給)
- L - Leader or Laggard(主導銘柄か、出遅れ銘柄か)
- I - Institutional Sponsorship(機関投資家による保有)
- M - Market Direction(市場の方向性)
それでは、各項目を詳しく見ていきましょう。
C:当期四半期利益(Current Quarterly Earnings)
原則:株価が大きく動く銘柄は、その直前に四半期決算が急激に良くなっている。
最も重要な基準の一つです。素晴らしい企業は、利益が大幅に、そして「加速しながら」伸びていく傾向があります。
チェックポイント:
- 直近の四半期EPS(1株当たり利益)が、前年同期と比べて最低でも25%以上増加しているか?
- トップクラスの銘柄は、しばしば70%以上の驚異的な伸びを見せます。
- 利益の伸びは加速しているか?
- (例:+20% → +35% → +60% のように、成長率自体が上がっているのが理想)
- 売上高も同時に伸びているか?
- コスト削減だけで作った利益ではなく、本業の成長が伴っているかを確認します(25%以上の売上増が目安)。
A:年間利益成長(Annual Earnings Growth)
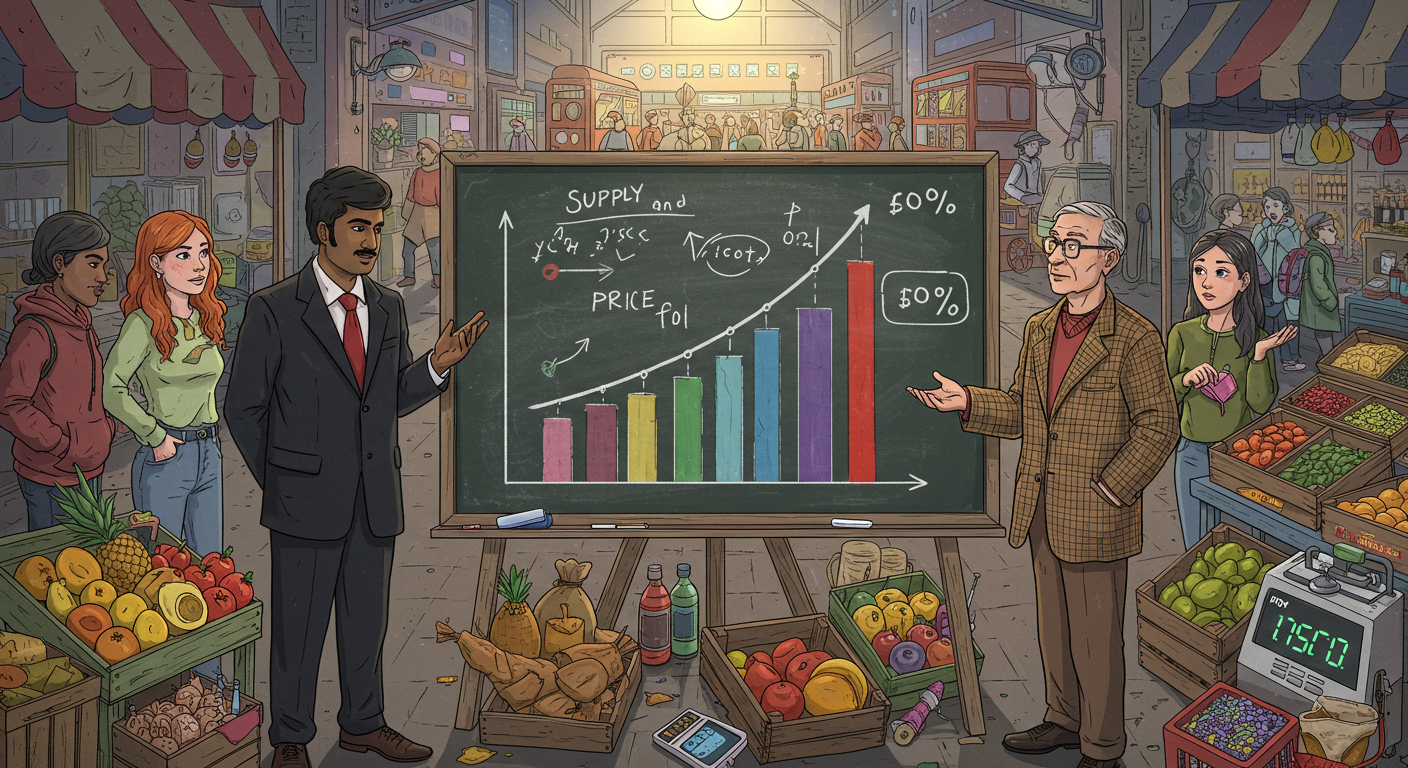
原則:一回の好決算だけでなく、過去数年間にわたって安定した成長実績がある。
一発屋ではなく、継続的に成長できる地力のある企業を探します。
チェックポイント:
- 過去3〜5年の年間EPS成長率が、毎年25%以上か?
- ROE(自己資本利益率)は17%以上か?
- ROEは、企業が自己資本をどれだけ効率的に使って利益を生み出しているかを示す指標です。25%〜50%あれば非常に優秀です。
N:新製品、新経営陣、新高値(New Products, New Management, New Highs)
原則:株価を大きく動かすには、何か「新しい」カタリスト(きっかけ)が必要。

株価が過去にない水準まで上昇するには、投資家を興奮させる新しい材料が不可欠です。
チェックポイント:
- 新しい要素はあるか?
- 業界の常識を覆すような新製品・新サービス(iPhoneの登場など)
- 優れた実績を持つ新経営陣への交代
- 業界構造を大きく変えるような法改正や技術革新
- 株価は新高値圏にあるか?
- オニールは「安値で買うな、新高値で買え」と説きます。株価が52週高値を更新するのは、その銘柄が強い勢いを持っている証拠です。52週高値から15%以内の株価が目安です。
S:株式の需要と供給(Supply and Demand)
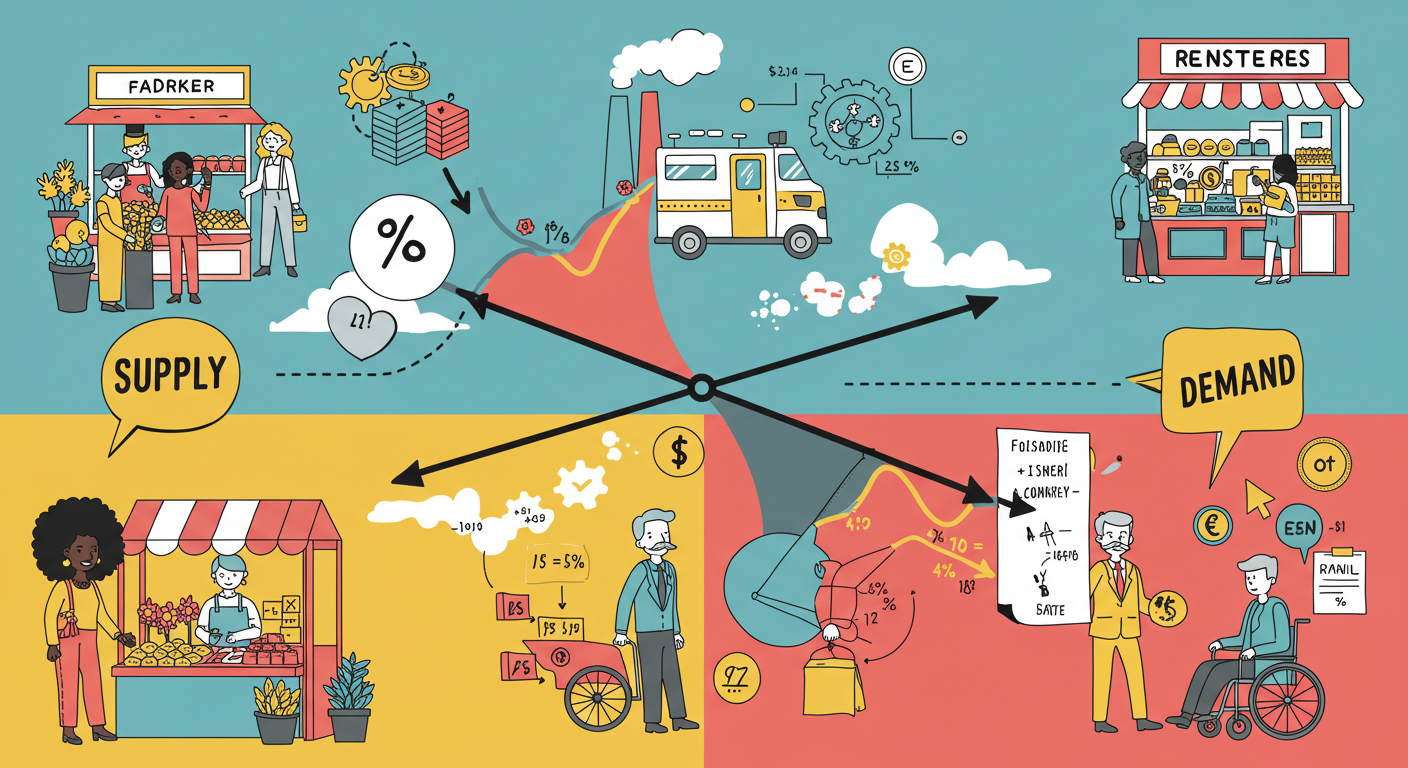
原則:需要が供給を上回れば、株価は上がる。
経済の基本原則です。発行済み株式数が少なく、多くの投資家が買いたいと思う株は、価格が上がりやすくなります。
チェックポイント:
- 発行済み株式数は多すぎないか?
- 株価が軽い小型〜中型株の方が、大きな上昇を期待しやすい傾向があります。
- 出来高は急増しているか?
- 株価が重要な価格帯(抵抗線)を突破する際に、普段より40〜50%以上多い出来高を伴う場合、それは機関投資家などの大口が積極的に買っているサインです。
L:主導銘柄か、出遅れ銘柄か(Leader or Laggard)
原則:同じ業界なら、最も勢いのある主導銘柄(リーダー)に投資する。
出遅れている二番手、三番手の銘柄ではなく、その業界を牽引する最強の銘柄を選びます。リーダーは最高の利益、最高の製品、そして最高の株価パフォーマンスを誇ります。
チェックポイント:
- RPS(レラティブ・プライス・ストレングス)レーティングは高いか?
- RPSは、過去1年間の株価パフォーマンスを市場の全銘柄と比較してランク付けした指標です(1〜99)。80以上であることが一つの基準となります。これは、その銘柄が市場の他の80%の銘柄よりもパフォーマンスが良いことを意味します。
I:機関投資家による保有(Institutional Sponsorship)
原則:「スマートマネー」と呼ばれるプロの投資家(機関投資家)が買っているか。

株価を大きく押し上げるには、年金基金や投資信託といった機関投資家の莫大な資金が必要です。
チェックポイント:
- 質の高い機関投資家が株主になっているか?
- 優れた運用実績を持つ、トップクラスのファンドが保有しているかは重要なサインです。
- 保有する機関投資家の数は増えているか?
- ただし、すでにあまりにも多くの機関投資家に保有されすぎている(過剰保有)銘柄は、何か悪いニュースが出た際に大きな売り圧力になるため注意が必要です。
M:市場の方向性(Market Direction)
原則:市場全体のトレンドに逆らわない。

どんなに優れた銘柄でも、株式市場全体が下降トレンド(弱気相場)であれば、株価は下落する可能性が高いです。オニールによれば、**「4銘柄のうち3銘柄は市場全体の動きに追随する」**とされています。
チェックポイント:
- 市場は明確な上昇トレンドにあるか?
- S&P 500やナスダックなどの主要な株価指数が上昇している時にのみ、買いを実行します。
- 市場の天井や底のサインを見極める。
- 弱気相場では無理に取引せず、現金で待機することも重要な戦略です。
CAN-SLIMのメリット・デメリット
メリット
- データに基づいている:100年以上の歴史的データから導き出された、実績のある手法。
- 包括的なアプローチ:ファンダメンタルズとテクニカルの両面から銘柄を分析。
- 規律が身につく:明確な売買ルールがあり、感情的なトレードを避けやすい。
デメリット
- 成長株に特化している:バリュー株(割安株)投資には向かない。
- 弱気相場に弱い:上昇相場で最大の効果を発揮するが、下落・横ばい相場では機能しにくいことがある。
- 相応の努力が必要:常に市場をチェックし、リサーチを続ける必要があるアクティブな手法。
まとめ:CAN-SLIMで大化け銘柄を見つけよう
CAN-SLIMは、単なるチェックリストではありません。それは、歴史上最も成功した銘柄のDNAを解読し、未来のスター銘柄を発掘するための設計図です。
| 基準 | チェックするポイント |
|---|---|
| C | 四半期利益は急増・加速しているか? |
| A | 年間利益は安定して成長しているか? |
| N | 新製品や新高値といった「新しい材料」はあるか? |
| S | 出来高を伴って需要が集まっているか? |
| L | 業界の主導銘柄(リーダー)か? |
| I | プロの機関投資家は買っているか? |
| M | 株式市場全体は上昇トレンドか? |
もちろん、この7つの基準をすべて完璧に満たす銘柄を見つけるのは簡単ではありません。しかし、このフレームワークを使って銘柄を分析する習慣をつけることで、あなたの投資判断はより論理的で、成功確率の高いものになるでしょう。
まずはウォッチリストを作成し、気になる銘柄がCAN-SLIMの基準をいくつ満たしているか、チェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。

